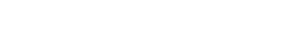世界的なベストセラーである『子どもが育つ魔法の言葉』から、実際に子育てで頻繁に使うことができる「魔法の言葉」を厳選して紹介します。
書籍『子どもが育つ魔法の言葉』とは?

『子どもが育つ魔法の言葉』はアメリカの教育コンサルタントであるドロシー・ロー・ノルトが書いた育児本で、アメリカや日本をはじめ世界各国で子育てに悩む親たちに愛読されています。
ドロシー・ロー・ノルトは保育園の子育て教室に勤務していた1954年に「子は親の鏡」という詩を発表しました。
子育て教室にやってくる悩める親達のために作ったものです。
この詩には、例えば「励ましてあげれば、子どもは、自信を持つようになる」「認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる」というように、親の子供への接し方がその子の人格形成に大きな影響を与えることがわかりやすく表現されています。
この詩は評判をよび世界中で翻訳されてたくさんの人々に読まれれるようになりました。
しかし、時代を経て間違った解釈をされるようになったため、詩の解説本として1990年代に『子どもが育つ魔法の言葉』を書き上げたのです。
『子どもが育つ魔法の言葉』にある、すぐに使える魔法の言葉
『子どもが育つ魔法の言葉』は、身近な事例を交えながら、とてもわかりやすく書かれています。
子供の気持ちはもちろん、日々懸命に子育てをしている親の気持ちにも寄り添った内容になっているので、子育てをしているママ・パパであれば誰もが共感して、実践したくなります。
しかし、本を読んだ直後はその通りやってみようと決意するのですが、なかなか長続きしないものです。
そこで、いつでも実践できるように、『魔法の言葉』の中でも特に使いやすい言葉をまとめて紹介します。
1.どうして、こんなことになってしまったの?
まずは、子供が失敗をしてしまったときの「魔法の言葉」を紹介します。
子供は毎日、失敗ばかりしています。
例えば、コップの牛乳をこぼしたり、おもちゃを壊したり、大切なものをなくしたり。
この本の「ついカッとなってしまったら」という節の中では、子供が失敗をしたとき、カッとなって怒鳴りつけるよりも、「どうして、こんなことになってしまったの?」と理由を聞いて、失敗の原因を自分で考えさせて、失敗から学ぶように導くべきであるとしています。
また、このような問いかけをすることで、その後に責任をとらせる(床にぼれた牛乳を拭かせるなど)時にもスムーズにいくとしています。
もし、責任をとらせているときにうまくできなければ、頑張りを認めてあげた上で「手伝うよ」といってサポートします。
2.どうすればよかったと思う?
次に、子供が悪いことをしたときの「魔法の言葉」を紹介します。
子供は悪いことをするときもあります。
例えば、おやつやおもちゃを一人占めしたり、ママやパパの大切なものを勝手に使ったり。
この本の「厳しく叱るよりも、子供を励ますほうがいい」という節の中では、このような悪いことをしたときには、厳しく叱って罪悪感を植え付けるのではなく、なぜそんなことをしたのか聞いたうえで、「どうすればよかったと思う?」と質問をして、考えさせるようにすべきであるとしています。
なぜなら、自分で考えて出した答えのほうがやる気がでるからです。
3.〇〇してね。偉いね。
次は、子供に何かをしてもらいたい時の「魔法の言葉」を紹介します。
何度言い聞かせても、子供はちっともその通りにしてくれません。
おもちゃで遊んだら片づけをする、ご飯を食べたら手洗い・歯磨きをする、服を脱いだら洗濯カゴに入れる、などなど、こうした日常の義務をなかなか果たしてくれないため、親としてはつい小言が多くなってしまいます。
本の「小言を言っても子供はよくならない」という節では、このような時、「また、おもちゃが出しっぱなしなんだから」と否定的な小言を言うのではなく、単に「おもちゃをかたづけてね」という肯定的な言い方をしたほうが、子供は聞く耳を持つとしています。
そして、実際に言ったようにできたら、「偉いね」と褒めることで、だんだん親の期待に答えようとするようになると言っています。
4.「どうしたの?」「どうしたらいいのかな?」
続いて、子供が何かに怒っているときの「魔法の言葉」を紹介します。
子供はおもちゃを貸してもらえなかったり、忙しいと言われて遊んでもらえなかったりして、親や兄弟、友達に対して怒ることがよくあります。
子供は怒った時にそれを言葉でうまく表現することができないため、モノを投げたり、蹴ったりするなどの態度で怒りを表そうとします。
本の「感情を上手に表現する」という節では、子供が怒っているいるときに「なに怒ってるの?」と先回りして言うのではなく、「どうしたの?」と子供に状況を話させて、その後に「どうしたらいいのかな?」と子供に考えさせるほうが、自分の気持ちを理解して、自分の感情を言葉で表現できるようになるとしています。
5.できるよ。もう一度やってみよう
最後は、子供に壁にぶつかってしまったときの「魔法の言葉」を紹介します。
子供は未熟であるがゆえ、できないことがたくさんあります。
例えば、きれいに字が書けない、パズルが解けない、上手に片づけられないなどです。
こんなとき、子供は「もうやだ!」「つまんない!」「できない!」と投げ出してしまこともあります。
この本の「子どもは、どんな時に親の同情を引こうとするのか」や「子どもを励ます」という節では、うまくいかなかったときに、「まだ難しいから、仕方ないよ」といって同情すると、自分にはできないのだと諦めてしまうかもしれないので、「できるよ。もう一度やってみよう」と励まして、うまくできるようにアドバイスを与えるべきだとしています。
子供は親に励まされると、やる気がでてくるのです。
番外編.ママを抱きしめてください!
番外編として、子供への「魔法の言葉」ではなく、日ごろ子育てや家事、仕事に奮闘しているママやパパが元気を出すための「魔法の言葉」を紹介します。
一生懸命頑張っているのに家族から頑張りを理解してもらえず、マイナス思考に陥ってしまうこともあるでしょう。
本の「みじめになってしまったら」という節で、ケイトというママが「誰も自分のありがたみを感じてくれていない」と落ち込んでいた時に、メッセージボードに「ママはすごい。賛成の人はママを抱きしめてください」と書き、それを見た子供たちもパパも次々に抱きしめてくれたというエピソードが紹介されています。
ママやパパの頑張りに対して、口には出さなくても本当はみんな感謝しているはずです。
だから、辛い時は思い切って自分から感謝してほしいと表現してもいいのではないでしょうか?
さて、今回紹介した言葉以外にも『子どもが育つ魔法の言葉』には、日々の子育てで役に立ちそうな実例や魔法の言葉がたくさん書かれています。
興味をもったママ・パパは一度読んでみてください。