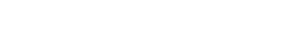厚生労働省が作成している「妊産婦のための食生活指針」は、妊婦さんに役立つ情報が満載です。
赤ちゃんにもママにも優しい食生活で健康的な妊娠生活を送りましょう!
そこで「妊産婦のための食生活指針」の主なポイントを分かりやすく解説していきます。
妊産婦のための食生活指針とは?
「妊産婦のための食生活指針」は妊産婦の健康支援のために厚生労働省が取りまとめた食事に関するガイドラインです。
医師、保健師、栄養士など母子健康に関する専門家が策定に関わっていますので、科学的根拠に基づた内容となっています。
妊娠中や授乳中の「食べ物」についての一般的な情報であれば、何よりもまず「妊産婦のための食生活指針」を参考にするのが望ましいと言えます。
スマホなどにパンフレットをダウンロードして活用することをお勧めします。
「妊産婦のための食生活指針」のポイント解説
それではどのような内容が記載されているのか3つのポイントで解説していきます。
1.妊娠中はどれくらい太ってもいいの?
「妊産婦のための食生活指針」には、妊娠中の「推奨体重増加量」が次のように示されています。
| 体格 | 推奨体重増加量 |
|---|---|
| やせ(BMI18.5未満) | 9~12kg |
| ふつう(BMI18.5~25.0未満) | 7~12kg |
| 肥満(BMI125.0以上) | 個別対応 |
※細かな注意事項があるため実際の「妊産婦のための食生活指針」も確認してください。
「やせている」「太っている」などの体格は「BMI(ボディーマス指数)」という数値で表されます。
つまり、「妊娠したら、まずは、自分の体格について正確に理解しておきましょう」ということになります。
BMIは次のような簡単な式で計算できますので、電卓を使って実際に計算してみましょう。
体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
体重が49kg、身長が158cmの場合
49 ÷ 1.58 ÷ 1.58 = 19.6(BMI)
「やせ」「ふつう」の人にとっては「意外と体重が増えてもいいんだな」と感じるかもしれませんが、この体重増加量は胎児や羊水による増加分を含んだ数値ですので油断は禁物です。
特に妊娠中期(16週)以降は、あっという間に体重が増えていきますので、妊娠初期はバランスのよい食事を心がけて体重が増え過ぎないようにすることが大切です。
なお、肥満の人はそうでない人と比べると妊娠・出産のリスクが高いため医師と相談したうえで自分に合った体重増加の目安を知っておく必要があります。
2.食べる量はどれくらい増やしたらいいの?
妊娠中・授乳中のママの栄養は、赤ちゃんの栄養にもなります。
健康な赤ちゃんを産み育てるためには、ママが赤ちゃんの分までしっかりと栄養を摂る必要があります。
では、どのタイミングで、どれくらい増やしたらいいのでしょうか?
妊産婦のための食生活指針にある「食事バランスガイド」には次のように示されています。
| 種類 | 妊娠前 | 初期 | 中期 | 末期・授乳期 |
|---|---|---|---|---|
| 主食 | 5~7(SV) | – | – | +1 |
| 副菜 | 5~6(SV) | – | +1 | +1 |
| 主菜 | 3~5(SV) | – | +1 | +1 |
| 乳製品 | 2(SV) | – | – | +1 |
| 果物 | 2(SV) | – | +1 | +1 |
※細かな注意事項があるため実際の「食事バランスガイド」も確認してください。
まず、妊娠初期は食べる量を増やす必要はありません。
増やすのは妊娠中期からです。
妊娠中期は副菜と主菜と果物をそれぞれ1SV増やします。
「SV」とは「お皿」とほぼ同じ意味で、副菜なら野菜の煮物や和え物などで小鉢1つ分、主菜であれば納豆や豆腐で小鉢1つ分、果物であればみかん1個分です。
エネルギー量に換算すると250kcal(ご飯150g)くらいの増加になります。
そして妊娠末期(28週~)は、妊娠前に比べて全種類を1SVずつ増やします。
主食なら小盛ご飯1杯分、乳製品なら牛乳コップ半分となります。
エネルギー量に換算すると500kcalくらいの増加になります。
妊娠中に増やす量も重要ですが、そもそも妊娠前の食事が「食事バランスガイド」に示されているようなバランスの良い食事だったのかチェックすることもより重要です。
先ほどの表をよく見て、例えば「主食(ご飯・パン)や主菜(肉・魚)はたくさん食べ過ぎていて、副菜と乳製品は少なかった」ということがあれば改善していきましょう。
3.妊娠中に食べたほうがよい食品はなに?
「妊産婦のための食生活指針(報告書版)」の内容に基づいて、妊娠中に食べておきたい食材について解説します。
カルシウムを補う『乳製品』
妊娠すると腸の機能が変化してカルシウムの吸収量がアップします。
そのため本来は妊娠したからといって余計に乳製品をとる必要はありません。
しかし、カルシウムの摂取量の目安は厚労省の「食事摂取基準」において20代で700mg、30代で600mgとされているのですが、実際にはこれを大きく下回る量しか摂取できていないという現状が日本人にはあります。
そのため妊娠したら意識して乳製品をしっかり摂る必要があります。
葉酸を含む『野菜』
葉酸は、赤ちゃんが神経管閉鎖障害になるリスクを下げる栄養素であるとされています。
特に胎児の神経系の器官形成が著しい妊娠3か月頃までは意識的に葉酸の多い食品を食べることが推奨されています。
具体的な食材としては「ほうれん草」「ブロッコリー」などの緑色野菜や「いちご」などの果物に多く含まれています。
手軽に健康補助食品を使うという方法もありますが、葉酸は摂取しすぎても良くないため注意して使いましょう。
鉄分を多く含む『動物性たんぱく質』
貧血に悩む妊婦さんはたくさんいます。
産科では鉄欠乏性貧血の治療するために鉄材を処方してくれますが、そうなる前に、しっかりとした食事で貧血を予防したいものです。
鉄分を含む食材としては、レバーなどのお肉や小松菜などの野菜がありますが、鉄の吸収率が高い食材は、お肉をはじめとした動物性食品です。
牛肉の赤身や豚・鳥のレバー、そして貝類に鉄分が豊富に含まれていますので、意識的にメニューに取り入れていきましょう。